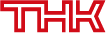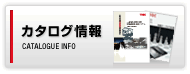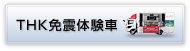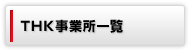Q&A
- 免震構造と他の構造との違いを教えて下さい。
- 地震の規模にもよると思いますが、THK免震システムはどの程度の効果がありますか?
- 直下型地震等の激しい縦揺れにも免震の効果はありますか?
- 風による影響はありますか?
- THK免震システムはメンテナンスが必要ですか?
- 免震を採用する際に、建物の構造材に制限はありますか?
- 戸建住宅に免震を採用する場合、どれ位の費用が発生しますか?
- 木造住宅に免震を導入する場合、上部構造の柱や壁を少なくできますか?
- 免震層の施工はどこが行うのですか?
- THK免震システムを導入するには、加盟料等が必要となりますか?
- 免震を採用する際に、敷地の制限はありますか?
- 免震住宅はどのような地盤でも建築可能ですか?
- ボーリング調査ではどの様な事を確認すれば良いですか?
- 建築確認における取り扱いはどのようになりますか?
- 免震住宅にした場合の優遇処置はありますか?
上記以外の詳細な内容に関するご質問等は、弊社ACE事業部までお問い合わせ下さい。
 免震構造と他の構造との違いを教えて下さい。
免震構造と他の構造との違いを教えて下さい。
『 免震・制震・耐震の違い』頁をご参照下さい。また、カタログ『 コンセプトブック』もご用意しておりますのでお気軽にご請求下さい。
 地震の規模にもよると思いますが、THK免震システムはどの程度の効果がありますか?
地震の規模にもよると思いますが、THK免震システムはどの程度の効果がありますか?
一例をあげると地震の横揺れを10とした時、1階で1.5(約6分の1)、2階で1.8(約5分の1)まで軽減することができ、建物内の家具や家財などの転倒・損傷を回避することが可能となります。対して非免震住宅では1階は10程度、2階は15程度に増幅されます。
 直下型地震等の激しい縦揺れにも免震の効果はありますか?
直下型地震等の激しい縦揺れにも免震の効果はありますか?
過去の大きな地震における建物の倒壊や家具類転倒の主な原因は、横揺れによるもので、縦揺れを起因とする大きな被害は生じていません。このことから、一般の免震構造は、地震の横揺れに対処することを目的としています。例えば、重力の大きさを10とした場合、阪神・淡路大震災(*)における横揺れの最大値は8、縦揺れの最大値は3程度のものでした。つまり、10を超える縦揺れが起こらない限り、建物や家具等が浮き上がる力は発生しません。仮に激しい縦揺れが生じた場合でもTHK免震システムの直動転がり支承CLBは引抜き力に抵抗できる機能を有するため、建物が浮き上がる心配はありません。
*阪神・淡路大震災(神戸海洋気象台 南北方向)における横揺れの最大値は818gal、縦揺れの最大値は332gal。重力加速度は980gal。
ガル[gal]とは、加速度の単位(cm/sec2)で、地震の大きさを示す指標の一つ。
 風による影響はありますか?
風による影響はありますか?
日常的な風により動くことはありません。台風等の暴風雨においてはゆっくりと動く可能性はありますが、仮に動いた場合でも復元機能がある為、中立位置に戻ります。
 THK免震システムはメンテナンスが必要ですか?
THK免震システムはメンテナンスが必要ですか?
免震装置を長期的に使用するためには、適度なメンテナンスが必要です。メンテナンスを施すことにより、一般的な建物耐用年数以上の使用が可能です。
*免震層の保守・管理システムについては弊社ACE事業部まで お問い合わせください。
 免震を採用する際に、建物の構造材に制限はありますか?
免震を採用する際に、建物の構造材に制限はありますか?
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など、構造材を問わず採用可能です。
 戸建住宅に免震を採用する場合、どれ位の費用が発生しますか?
戸建住宅に免震を採用する場合、どれ位の費用が発生しますか?
建物の構造及び平面形状、敷地地盤条件により異なりますので、弊社ACE事業部まで お問い合わせください。
建物プランが定まっておりましたら、概算見積をさせて頂きます。
 木造住宅に免震を導入する場合、上部構造の柱や壁を少なくできますか?
木造住宅に免震を導入する場合、上部構造の柱や壁を少なくできますか?
免震住宅の上部構造は非免震住宅のそれと同様に、耐震等級*の等級1以上で設計する必要があるため、その範囲を逸脱して柱や壁(壁量)を少なくすることは出来ません。ただし、免震構造にすることで等級1であっても等級3と同等の耐震性を有する建物として扱われます。鉄骨造・鉄筋コンクリート造などについては、設計者の判断によるところがありますので お問い合わせください。
*耐震等級・・・住宅性能表示制度における建物の耐震性を示すもので、等級1/等級2/等級3があり、等級1は建築基準法レベル、等級2は等級1の1.25倍、等級3は1.5倍となっています。
 免震層の施工はどこが行うのですか?
免震層の施工はどこが行うのですか?
THK免震システムの施工は、工務店・ハウスメーカー又は施工専門業者が行います。
尚、免震装置の設置等に関するご相談等は、弊社ACE事業部まで お問い合わせ下さい。
 THK免震システムを導入するには、加盟料等が必要となりますか?
THK免震システムを導入するには、加盟料等が必要となりますか?
当システムはオープン品ですので、基本的にはどなたでも利用可能となっております。
 免震を採用する際に、敷地の制限はありますか?
免震を採用する際に、敷地の制限はありますか?
大地震時に基礎(地盤)と建物間に20cm~40cm程度の応答変位(*)が生じます。そのため、建物と周辺構造物あるいは隣地境界(道路境界)との水平クリアランス(用途により3種類あり。図表参照)を確保する必要があります。また、エアコン室外機や室外給湯器などを設置する際にも同様に必要クリアランスを確保するか、建物と一体で設置する必要があります。
*応答変位とは、地震を受けた時に免震建物が動く変位量を意味します。
| 免震建物の水平クリアランス | ||
|---|---|---|
| A | 第三者の通行に使用される場合 | 応答変位 +80cm |
| B | 居住者の通行に使用される場合 | 応答変位 +20cm |
| C | A, B以外の場合(軒先など) | 応答変位 +10cm |
 免震住宅はどのような地盤でも建築可能ですか?
免震住宅はどのような地盤でも建築可能ですか?
一般的な免震住宅が設計される方法では、「第一種地盤又は第二種地盤(地震時に液状化するおそれの無いものに限る)」と規定されています。尚、液状化に関する判断は地盤調査の結果を基に行ないます。また、傾斜地や崖地の場合については検討が必要な場合がありますので お問い合わせください。
 ボーリング調査ではどの様な事を確認すれば良いですか?
ボーリング調査ではどの様な事を確認すれば良いですか?
主として、免震設計上必要となる、地震力を入力する「工学的基盤の確認」が必要となります。
尚、「工学的基盤の確認」とは「せん断波速度 Vs≧400m/s かつ 5m 以上の厚さを有する地盤の確認」を指し、これは免震設計を行う際の必要不可欠な要素です。
 建築確認における取り扱いはどのようになりますか?
建築確認における取り扱いはどのようになりますか?
一般的な戸建免震住宅では、免震層の構造計算を行い、建築確認の申請時に免震層の構造計算書と設計図面を添付します。その際、「構造計算適合性判定」の対象建物となります。
 免震住宅にした場合の優遇処置はありますか?
免震住宅にした場合の優遇処置はありますか?
長期固定金利の住宅ローン[フラット35]S(優良住宅取得支援制度)において、免震建築物(住宅性能表示制度の評価方法基準1~3に適合しているもの)は、借入金利を低減する処置がとられています。詳しくはこちらをご覧下さい。