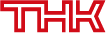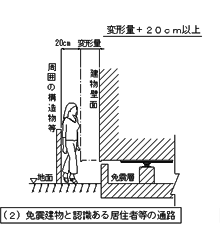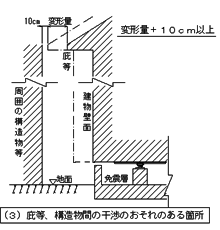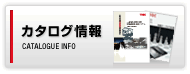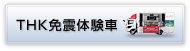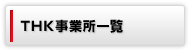設計・施工のポイント
免震建物導入の流れ
一般的な戸建住宅の場合、免震の導入は下図、中央のルートで確認申請をすることになります(告示免震)。その際、構造計算適合性判定(ピアチェック)の対象にもなります。
免震建物の設計ルート
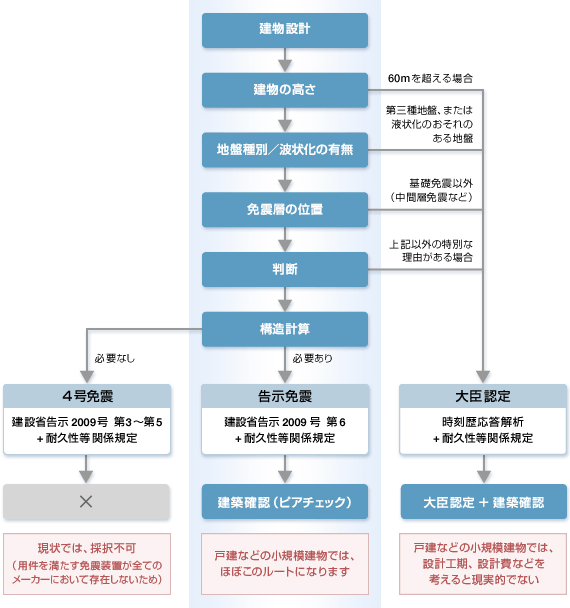
免震住宅計画における注意点
免震住宅計画にあたっては以下の3点に注意する必要があります。
1. 建設地点の地盤状況確認
建物敷地内で地盤調査(ボーリング)を行い、表層地盤の状況※(地層分布、硬軟)を調査し、「地盤種別」、「液状化の有無」を算定します。また、「表層地盤の増幅特性(揺れやすさ)」も算定し、構造計算に用いる建物基礎位置に伝わる地震力を算定します。
| 地盤種別 | 液状化の有無 | 構造計算法 | 申請手法 |
|---|---|---|---|
|
第1種地盤
(硬質地盤) |
- | 告示2009号第6による構造計算 +耐久性等関係規定 (構造方法2) |
確認審査 +構造計算適合性判定 |
|
第2種地盤
(普通地盤) |
無し | ||
| 有り | 時刻歴応答解析 +耐久性等関係規定 (構造方法3) |
性能評価機関での性能評価 +国土交通大臣認定 |
|
|
第3種地盤
(軟弱地盤) |
- |
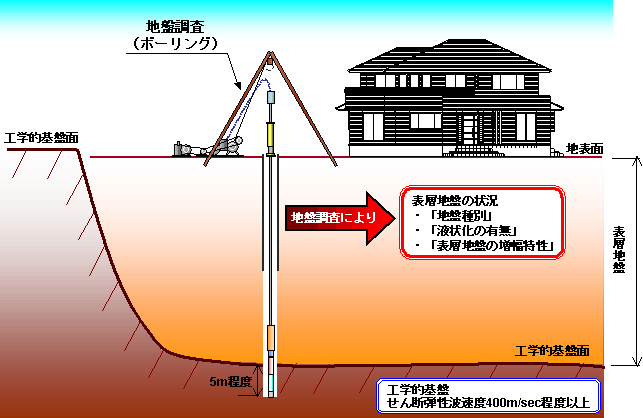
※ボーリングの掘進深度の目安として、工学的基盤(せん断弾性波速度400m/sec程度以上)の層厚を5m程度確認するまで必要です。
※急傾斜地・崖地あるいは地層の傾斜が大きい(傾斜角5°程度以上)場合は、申請手法が「性能評価機関での性能評価+国土交通大臣認定」となります(傾斜角は近隣の地盤調査データ等から判断します)。
2. 周辺の構造物あるいは隣地境界との地震時水平クリアランスの確保
大地震時に基礎(地盤)と建物間に20cm~40cm程度の応答変位が生じます。そのため、建物と周辺の構造物あるいは隣地境界(道路境界)との水平クリアランスを確保する必要があります。(用途により下表、下図に示す3種類あります)また、室外給湯器やエアコン室外機等を設置する際にも同様に必要クリアランスを確保するか、建物と一体で設置する必要があります。
| 免震建築物に求められる水平クリアランス | ||
|---|---|---|
| A | 第三者の通行に使用される場合 | 応答変位 +80cm |
| B | 住居者の通行に私用される場合 | 応答変位 +20cm |
| C | A,B以外の場合(軒先など) | 応答変位 +10cm |

室外給湯器水平
クリアランス確保
室外機建物側設置例
3. 配管設備などの構造
免震住宅は、地震時等に基礎(土地)に対して水平方向に変位しますので、上下水道・ガス等の配管設備はフレキシブルな構造とし、電気・電話等の配線類には余長を保たせてください。

フレキシブルな排水管と水道管

雨樋は基礎部と上部構造の境界で縁切り処置を行ってください
免震建物施工手順